こんにちは、ハルです。
テキストを読んでいるのに、頭に入ってこない。 黙読しても、何を読んだか思い出せない。
そんな経験はないだろうか?
実際、私も何度もそう感じてきました。 だがあるとき、「音読してみる」と、驚くほど内容が頭に残ることに気づいたのです。
資格勉強というと、机に向かって黙々とテキストを読むイメージが強いかもしれない。 しかし、声に出して読む=音読は、学習効果を飛躍的に高める可能性を秘めていると私は思います。
この記事では、資格勉強における“音読”の効果と、その具体的な活用法について紹介します!
なぜ音読が効果的なのか
音読が効果的な理由は、大きく分けて3つある。
1. 複数の感覚を使うから

音読では、「目で読む」「声に出す」「耳で聞く」といった複数の感覚を同時に使う。
これは心理学でも「マルチモーダル学習」と呼ばれ、 視覚・聴覚・運動感覚などを組み合わせて学習することで、記憶の定着が促進されるとされています。
2. 理解不足に気づけるから

音読すると、文の構造や意味がわからない箇所でつまずくことがある。 それが“理解できていない部分”であり、復習のヒントにことがあります。
黙読では読み飛ばしてしまうような違和感も、音読なら引っかかるのです。 「ひっかかる」ことで、理解を深めるきっかけになるのです。
3. 繰り返しやすいから
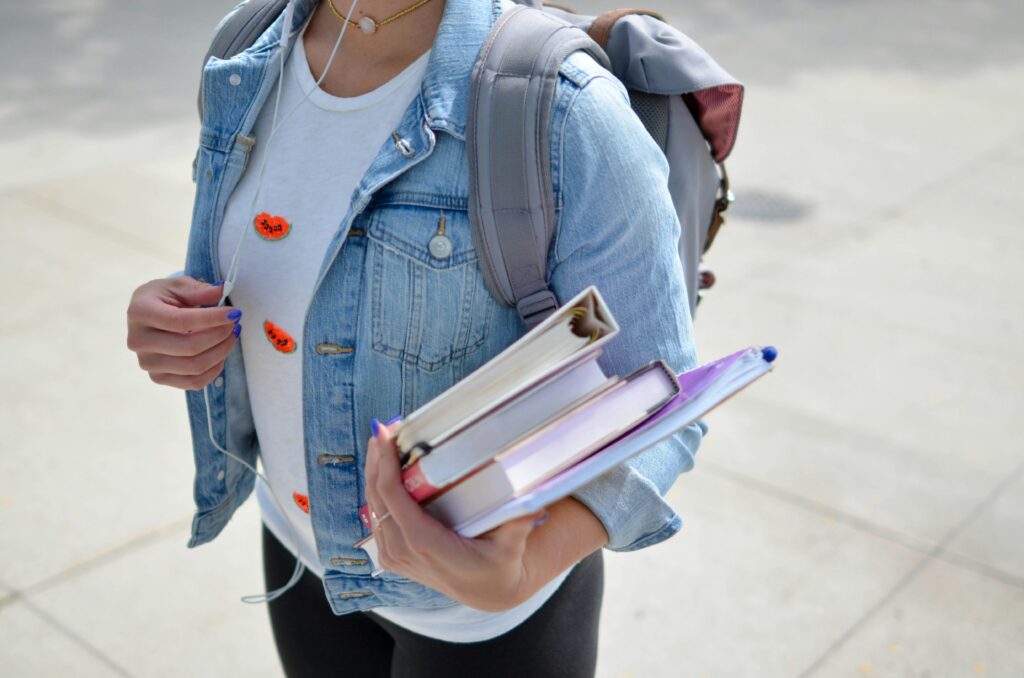
音読は黙読に比べて能動的で、集中力が持続しやすいです。 また、リズムがあることで繰り返しやすく、語呂合わせのように記憶に残ることも。
1日10分の音読を毎日続けるだけでも、記憶の定着率は大きく変わると実感している。
実際にやっている音読の使い方
私は不動産鑑定士の勉強を進める中で、音読を取り入れる場面を工夫してきました。
▶ 鑑定評価基準
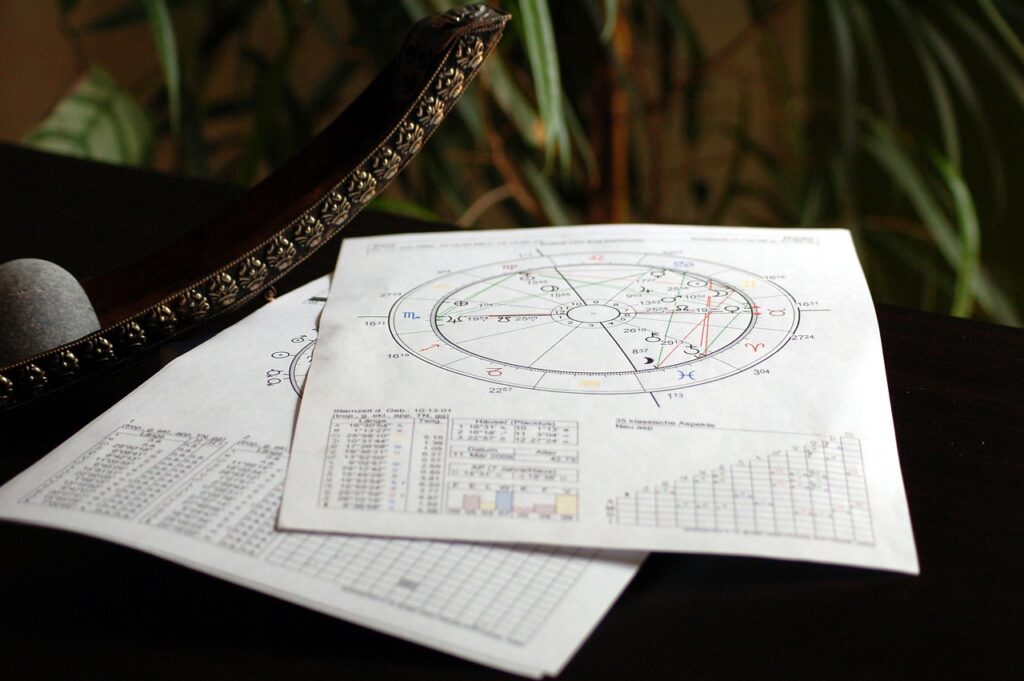
鑑定評価基準は、独特な言い回しや難解な構文が多いです。
これを黙読するだけでは理解しにくいため、音読しながら「意味のまとまり」を意識して読んでいます。
また、単語ごとではなく「語句のかたまり」で区切って読むと、文の構造が明確になります。 慣れてくると、音読しながら「この表現は前に出てきたものと対応してるな」と気づけるようになるのです。
一文いちぶんが長い文章には、音読が最適である。▶ 行政法規の数字や条件
都市計画法や建築基準法など、細かな数値や条件が頻出する分野では、音読が非常に有効です。
数字は目で見るだけでは混同しやすいが、声に出して覚えると記憶に残りやすい。
「○年以内」「○㎡以上」「○%以下」といったフレーズは、一定のリズムで繰り返すことで定着しやすくなる。
私は、苦手な数字をリストアップしておき、朝の時間に5分だけ音読する習慣を作っています。 これだけでも忘れにくくなったと感じています。
▶ 過去問の選択肢
過去問の選択肢を音読すると、「この表現、なんか変だな」といった違和感に気づきやすくなります。
例えば、選択肢AとBが似ているようで微妙に違う場合、声に出すことで「違い」が際立つ。 特に誤りを含む選択肢は、読むよりも声に出す方が「不自然さ」をキャッチしやすいです。
なので、私は、過去問を解くときに音読を取り入れることもある。また、正解肢を何度も音読しておくと、本番でも“聞き覚え”で答えが思い出せるようになると思います。
音読を続けるコツ
音読の効果を最大限に活かすには、無理なく続けられる形を整えることが重要です。
・一人で声を出せる環境をつくる

早朝の部屋、大学の空き教室、誰もいないバイト先の控室など、短時間でも音読できる環境を見つけておきましょう。
周囲の目を気にせず声を出せる場所をあらかじめリストアップしておくと、習慣にしやすいです。
おすすめは、自宅。笑・「覚えたいところだけ声に出す」
すべてを音読しようとすると疲れるため、重要語句や覚えにくい部分だけに絞るのがポイントです。
・録音して聞き直す
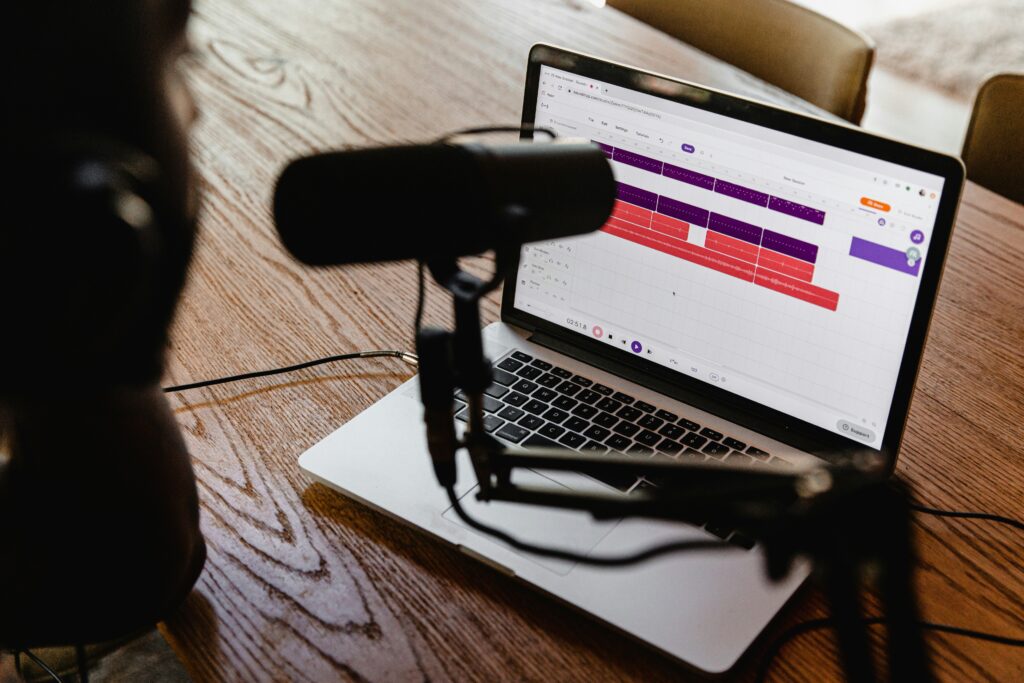
自分の声で録音した音源を通学中などに聞き返すことで、インプットを繰り返せます。
最初は恥ずかしいと感じるかもしれないですが、自分の声だからこそ「どこが覚えづらいか」がわかる利点もあります。
録音はスマホのメモアプリなどで十分。完璧な音質より「聞き流せる気軽さ」を優先するとよいと思います。
まとめ
音読は、記憶と理解の両方に効果があります。
資格試験のような情報量が多い試験では、「声に出す」ことで得られる感覚的な記憶が非常に有効です。
読むだけじゃ物足りないと感じたら、声に出してみる。 それだけで、記憶の定着も、理解の深さも、大きく変わるはず。
音読は、机に向かっているときだけの勉強法ではないです。 歩きながらでも、バイト前でも、通学中でもできる「シンプルで強力な武器」だと感じています。
誰にでもできて、続けやすい。 だからこそ、もっと多くの人に取り入れてほしい勉強法です。
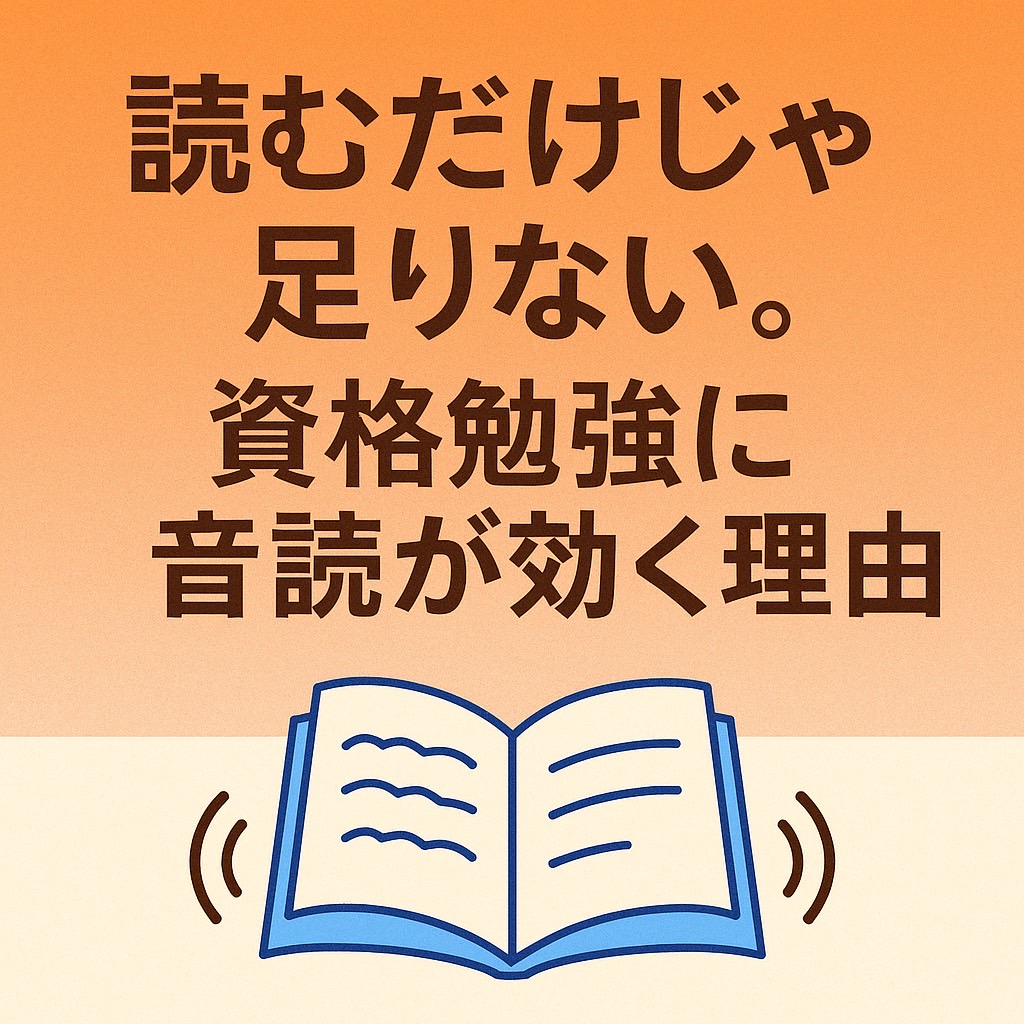

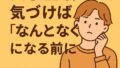
コメント