はじめに:宅建の勉強スケジュール、どう立てる?
宅建を独学で目指すと決めたとき、まず悩むのが「スケジュールの立て方」です。
毎日どれくらい勉強すれば間に合うのか? 3ヶ月? 半年? 1年?
自分のペースに合ったスケジュールを立てられなければ、せっかくのやる気も途中でしぼんでしまいます。
私自身、大学の授業やバイトと両立しながら宅建に合格しましたが、最初に“無理のないスケジュール”を決めたことが合格の分かれ道だったと実感しています。
この記事では、実体験をもとに「宅建のスケジュール例」を3パターンに分けて紹介します。
- 3ヶ月で一気に合格を狙うプラン
- 半年でじっくり確実に合格を目指すプラン
- 1年かけて無理なく合格を目指すプラン
それぞれに向いている人のタイプや注意点も解説しているので、自分にぴったりのペースを見つける参考にしてみてください。
私が実際に遂行した計画はこちらの記事で紹介しています
宅建合格に必要な勉強時間はどれくらい?
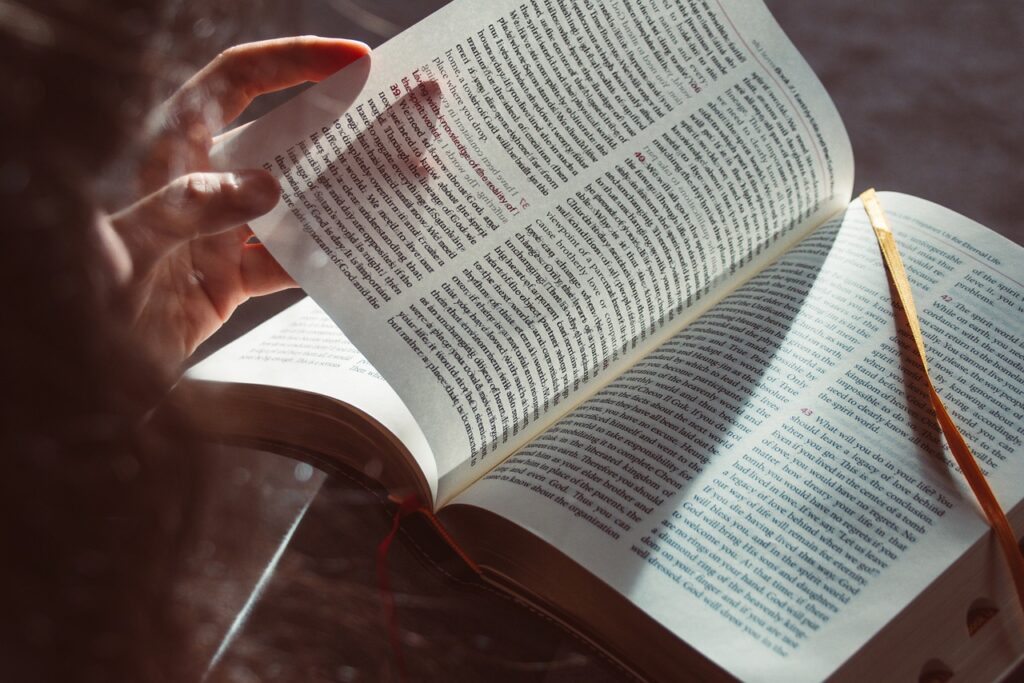
宅建試験に合格するために必要とされる勉強時間は、一般的に300〜400時間と言われています。
この数字だけ見ると少なく感じるかもしれませんが、独学の場合は“勉強の質”と“継続”が鍵になります。
たとえば、1日1時間のペースで勉強すれば、およそ1年で365時間。
逆に、3ヶ月で合格を目指す場合は、1日あたり3〜4時間を確保する必要があります。
「いつまでに合格したいか」よりも大切なのは、“1日あたりどれくらいの時間を取れるか”です。
宅建は範囲も広く、途中で挫折する人も多い試験です。だからこそ、最初に自分の生活に合った現実的なスケジュールを立てることが、合格への第一歩になります。
スケジュール例①|3ヶ月で合格を目指す場合

短期間で一気に合格を狙うなら、3ヶ月で合格を目指すプランがあります。
この場合、必要な勉強時間は約300〜400時間とされているため、1日あたり2.5〜3時間以上の確保が必須です。
平日はインプット、休日は過去問演習と模試を組み込むのが効率的です。
私も実際に夏休み期間を活用して集中して勉強した経験がありますが、「今日はここまでやる」と毎日ゴールを設定することが継続のコツでした。
また、直前期(試験の2〜3週間前)には、実際の試験時間に合わせた模試形式の演習を最低1回はこなしておくと、本番での焦りを軽減できます。
このプランは、すでにある程度勉強習慣が身についている人や、短期集中で一気にやりきりたいタイプの方に向いています。
スケジュール例②|半年で合格を目指す場合

半年かけて合格を目指すプランは、最もバランスがとれた現実的なスケジュールです。
この場合、必要な勉強時間を300時間とすると、1日あたり1.5時間前後の学習で到達できます。
前半の3ヶ月はテキストを使ってインプット(知識の習得)に集中し、後半の3ヶ月で過去問演習とアウトプット中心の学習に切り替えると効果的です。
平日は朝や通学中のスキマ時間でテキストを読み、週末にまとめて過去問を解くというスタイルです。
特におすすめなのは、毎月1回「進捗チェック日」を設けること。
月末に「どこまで進んだか」「理解度はどうか」を振り返るだけで、学習の精度がグッと上がります。
この半年プランは、大学生や社会人など、毎日のスキマ時間を上手く活用できる人に向いています。
スキマ時間の活用方法については、こちらの記事でどうぞ
スケジュール例③|1年かけてじっくり目指す場合
1年間かけて合格を目指すプランは、無理のないペースで勉強を進めたい人に適しています。
1年で300時間の学習を目指すなら、週に6〜7時間(1日あたり30分前後)の勉強時間を確保すれば十分です。
このプランでは、年間を大きく3つのフェーズに分けて考えると効果的です。
- 春〜初夏(4〜6月):基礎固め期間
- 夏〜初秋(7〜9月):アウトプット強化期間
- 秋〜試験直前(10月上旬):仕上げ・模試・総復習期間
私も、もし1年かけて取り組んでいたとしたら、「1週間ごとのテーマを決める」やり方をしていたと思います。
「今週は宅建業法だけ」「来週は民法」など、細かく分けることで進捗が見える化し、モチベーション維持につながります。
このプランは、仕事や育児などで忙しい方や、他の資格と並行して学習している方におすすめです。
スケジュールを立てるときのコツ
スケジュールを立てるときに一番大切なのは、完璧を目指さないことです。
私自身、理想のプラン通りに進んだ日は少なかったですし、何度も「今日やれなかった…」と落ち込んだこともあります。
そこで効果的だったのが、「最低ライン」「現実ライン」「理想ライン」の3段階でタスクを考える方法です。
- 最低ライン:これだけはやる(例:過去問1問だけ解く)
- 現実ライン:無理せずできる分量(例:テキスト1単元+1問)
- 理想ライン:調子が良い日に狙う量(例:過去問3問+復習)
段階を分けておけば、「今日は最低ラインできたからOK」と思えるようになり、継続へのハードルが一気に下がります。
また、模試や復習に使う“バッファ日”をあらかじめスケジュールに組み込んでおくことも大切です。
週に1日は「見直しの日」「予備日」を確保しておくことで、急な予定やモチベーションの波にも柔軟に対応できます。
私はこうしてスケジュールを立てていた
私自身、宅建の勉強を始めた当初は、大学の授業とバイトをこなしながらの学習でした。
まとまった勉強時間を取るのは難しかったので、スキマ時間を“積み重ねる”スタイルを選びました。
たとえば、通学中の電車の中でテキストを音読したり、昼休みに一問一答を1〜2問解いたり。
バイト前に15分だけでも参考書を開くようにしていました。
勉強時間としては、平日は1〜1.5時間、休日に3〜4時間ほど。
全休の日や長期休暇には、重点的に「過去問演習+復習+記録の見直し」を行っていました。
また、スケジュール帳に毎日の勉強内容と達成度を簡単にメモする習慣をつけていました。
「できた」「できなかった」と記録しておくだけで、自分のリズムがつかめるようになり、次のスケジュール調整もしやすくなります。
まとめ|あなたに合ったスケジュールで、宅建は取れる

宅建は、確かに勉強量の多い資格です。
ですが、計画的に取り組めば、独学でも十分に合格は狙えます。
大切なのは、生活リズムに合ったスケジュールを組み、無理なく継続すること。
「最低ラインでもいい」と自分を許しながら、習慣化を目指す方が、最終的には合格に近づきます。
この記事では、以下の3つのプランを紹介しました:
- 3ヶ月集中プラン
- 半年じっくりプラン
- 1年ゆるやかプラン
それぞれの生活スタイルや性格に合わせて、最適な方法は変わってきます。
ぜひ、自分に合ったペースで、少しずつ合格に近づいていってください。





コメント