はじめに
宅建の勉強を始めると、多くの人が最初にやるのはインプット学習です。 テキストを読む、講義を聞く、ノートをまとめる…すべて必要なことではありますが、それだけでは不十分。 実際に私も、インプット中心の学習で伸び悩んだ時期がありました。
この記事では、大学に通いながら宅建を取得した私が実際に合格するために意識して取り入れた『アウトプット重視の勉強法』について、具体例とともに紹介します。
なぜ“読むだけ”では定着しないのか?
テキストを読むと『わかった気』になることがありますが、実際には記憶に定着していないことがほとんどです。
特に宅建は、法律用語や判例、数字など細かい知識を問われるため、ただ理解するだけでは不十分。
『知っている』から『使える』に変えるためには、知識を繰り返し引き出す=アウトプットが必要です。 心理学的にも、“思い出す行為(想起)”は記憶を強化する効果が高いとされています。
私が実践していたアウトプット勉強法5つ
では、私が実際に宅建合格のために取り入れていたアウトプットの方法を紹介します。
① 過去問は早めに着手。解いてから学ぶスタイル
多くの人が『一通りインプットしてから過去問』と考えがちですが、私は早い段階から過去問に手をつけました。 分からない問題が多くてもOK。
重要なのは、解いたあとに解説を読み、なぜ正解なのか・なぜ間違ったのかを整理すること。 最初はボロボロでも、回数を重ねるうちに徐々にパターンが見えてきます。
② 『答えを出す』より『説明できる』を重視
答えを見て納得して終わるのではなく、自分の言葉で理由を説明できるようにしました。 『Aが正解なのは、Bというルールに基づくから』と、1問1問にロジックを持たせることで、応用力がつきます。
③アウトプット用アプリを活用
宅建の一問一答アプリを使って、スキマ時間にもアウトプット。 アプリの良いところは、答えが即時に確認できて、繰り返しやすいこと。
スマホがあればできるので、電車が混んでいて座れなくてもできるのがメリット。 通学中・休憩中など、短時間でも毎日継続しました。
④ 音読と口頭説明で知識を“自分の言葉”に変換
重要なポイントや引っかかりやすい内容は、声に出して読んでいました。 また、自分が他人に教えるつもりでしゃべると、理解が浅いところがすぐに見えてきます。「教えるつもり勉強法」はすごく有効で、私は、自分がわかっていないところによくこの用法を取り入れています。
この勉強法は、分かったつもりでも本当に理解できていなければ学習を進めることができずにもどかしく感じて、理解できていない原因は何なのかを解明することができます。
アウトプット中心にしてからの変化
アウトプット型に切り替えてから、明らかに『理解の深さ』が変わりました。 特に、過去問の正答率が安定し、初見問題への対応力もアップ。 試験直前には『この問題、考えればいける』と思える自信がついたのを覚えています。
まとめ
宅建に限らず、資格試験は“使える知識”が求められる世界だと思います。 どれだけ多くの情報を読んでも、頭の中から引き出して使えるようにならなければ意味がない。 もし、今『覚えたはずなのに問題が解けない』と感じているなら、ぜひアウトプット重視の勉強法を取り入れてみてください。
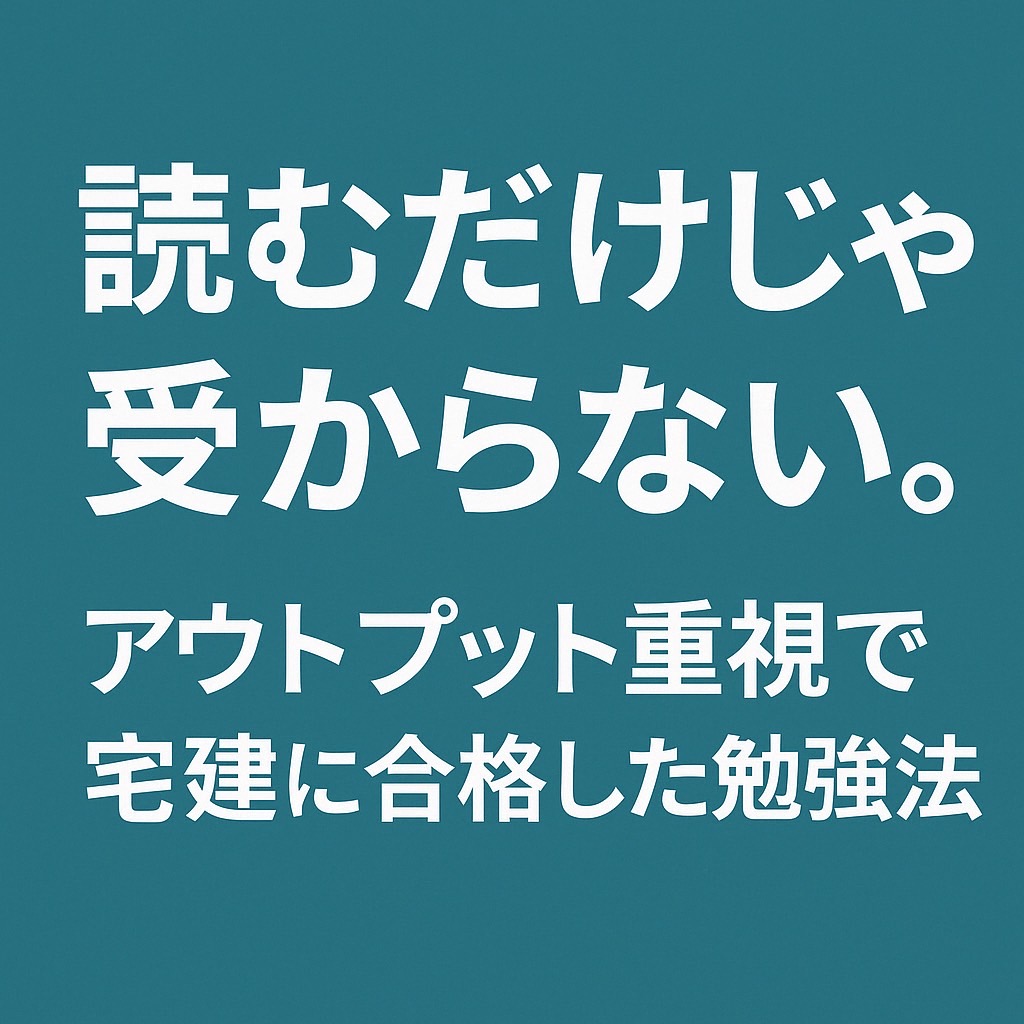
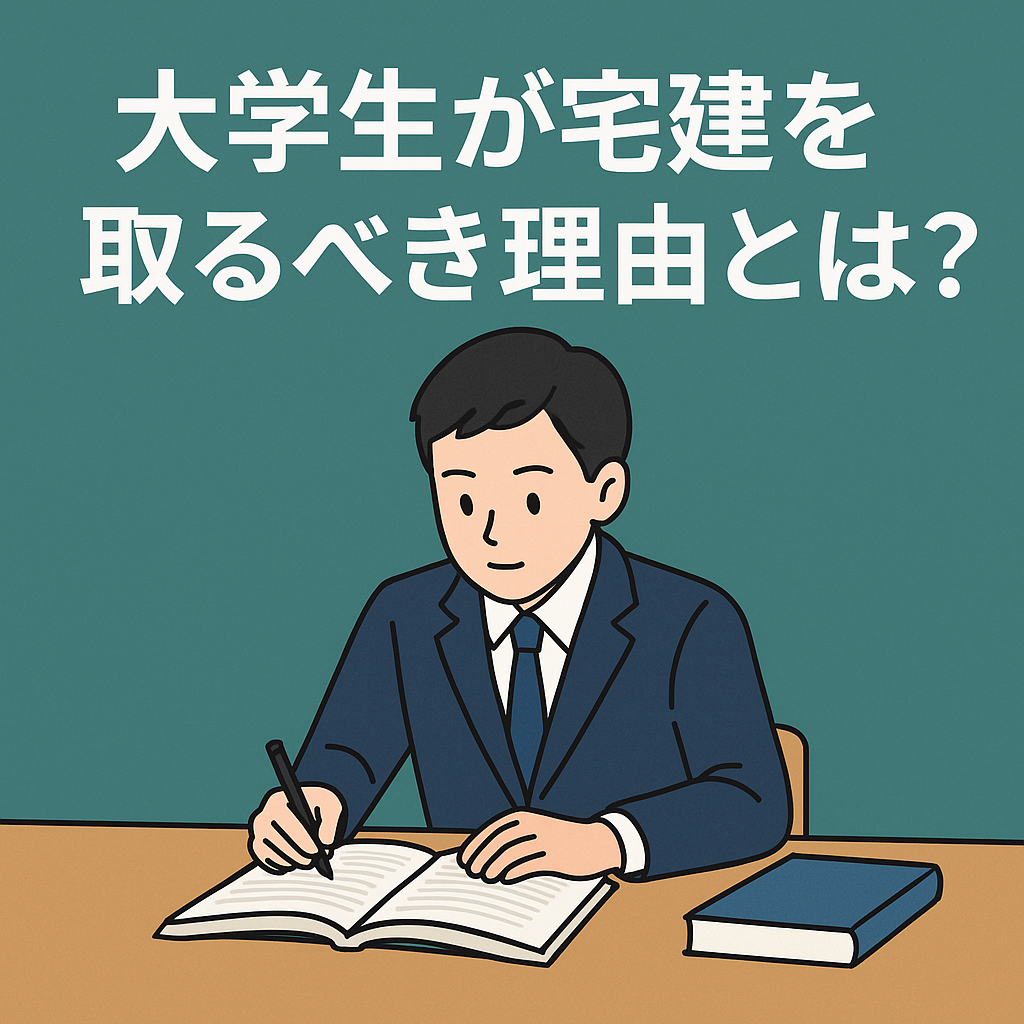

コメント