こんにちは、ハルです。
宅建の勉強は、正直しんどかったです。
民法の条文、過去問、聞き慣れない用語……。
でも、やりきってみて、得られたものは想像以上に大きかった。
ただの資格ではなく、勉強のスタイル、考え方、自信、すべてに影響を与えてくれました。
✅この記事では、大学生の私が宅建を取って「本当によかった」と思えた5つのことを紹介します。
1「勉強する力」がついた
宅建の勉強は、内容そのものも重要ですが、
それ以上に「毎日やること」「継続すること」の大切さを教えてくれました。
民法や宅建業法など、初めて学ぶ分野ばかりで、最初は全く歯が立たなかったけれど、
毎日コツコツ積み上げていくうちに、ちゃんとできるようになっていく実感がありました。
学ぶときの姿勢、インプットとアウトプットの切り替え、
暗記の工夫、計画の立て方……
この「勉強する力」は、今勉強している、不動産鑑定士にも活きていると感じます。
2自信がついた(=何かをやり切った経験)

宅建を取ったことそのものより、
「最後までやりきった」という経験が、自分の中に残りました。
途中で何度も挫折しかけたけれど、試験が終わって合格通知を受け取ったとき、
「自分でもここまでできるんだ」と思えたのは、何よりの収穫でした。
これは、就活の面接やエントリーシートにも自然とにじみ出る経験だと思っています。
3法律や不動産のニュースがわかるようになった
「用途地域」「市街化調整区域」「重要事項説明」
以前なら聞き流していた言葉が、勉強後には意味を持って聞こえてくるようになりました。
街を歩いていても、看板や再開発の掲示が気になるようになったり、
身近な不動産の広告の文言にも敏感になったり。
宅建の勉強は、「試験に受かるため」だけでなく、
暮らしの中で使える“知識の視点”を与えてくれました。
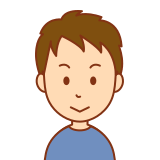
『地面師たち』にも、出てきましたね
4資格が“選択肢”になる

宅建は、実務で使える国家資格でもあり、
持っていることでできることが増える資格でもあります。
賃貸・売買・管理……
どんな方向に進むにしても、「宅建を持っているかどうか」は分かれ道になる場面がある。
また、私は今、不動産鑑定士の勉強をしていますが、
宅建を通して得た“基礎体力”が、間違いなく役立っています。
今、宅建に挑戦しようとしている人へ
宅建の勉強を始めたころは、先が見えずに不安でした。
でも、「わからないなりに毎日進める」ことで、少しずつ景色が変わってきて、
最終的には「やってよかった」と心から思える経験になりました。
試験の合否以上に、「がんばった」という事実が、今も自分の支えです。
これから宅建に挑戦しようとしている大学生の方に、
少しでも勇気やヒントを届けられたらうれしいです。
私の宅建試験勉強法は、こちらの記事でどうぞ
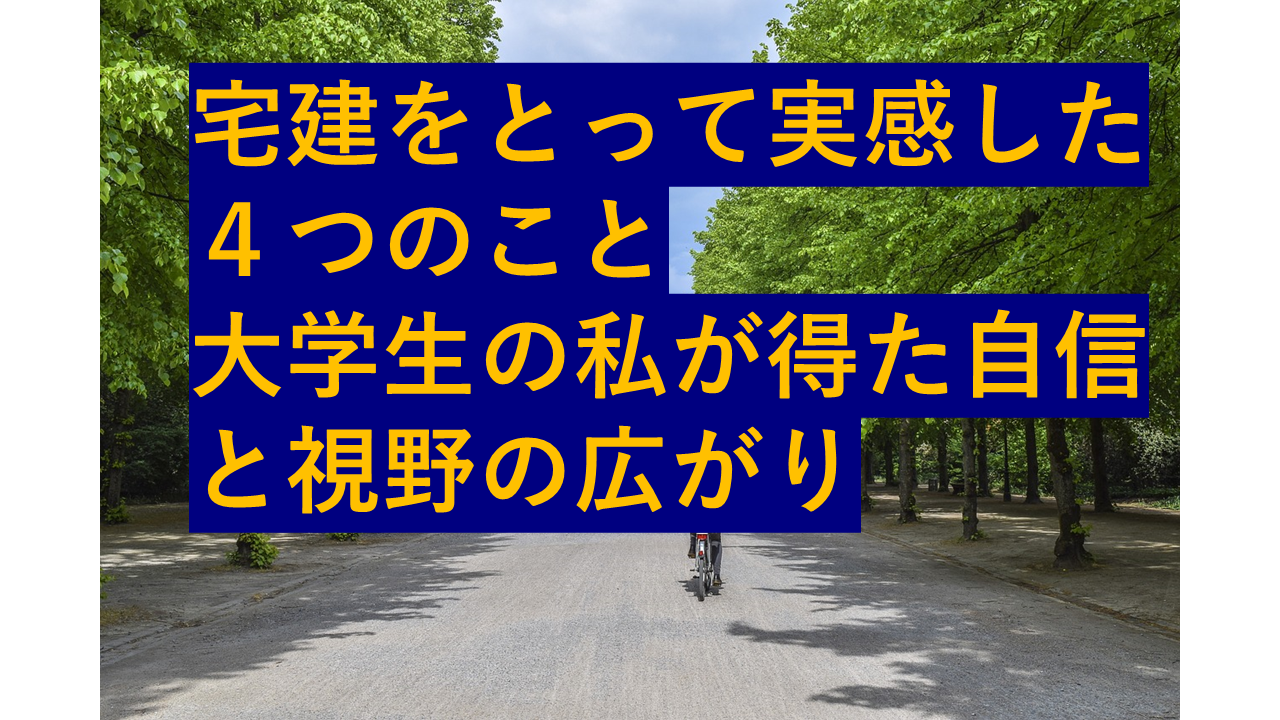



コメント