こんにちは、ハルです。
宅建や不動産鑑定士を勉強していると、必ず出てくる言葉「都市計画区域」。
用途地域を理解するためにも、この都市計画区域の概念は欠かせません。
✅この記事では、都市計画区域の基本と種類、そして勉強のコツまで、できるだけシンプルかつ詳しく解説していきます!
都市計画区域とは?

都市計画区域とは、道路・公園・住宅地・工業地帯など、街づくりを計画的に進めるために設定されるエリアのことです。
無秩序な開発を防ぎ、生活しやすく、安全な都市環境を整備することを目的としています。
都市計画区域の設定は、都道府県知事または国土交通大臣が行い、市町村の意見も考慮されます。
また、都市計画区域内では、用途地域の設定や建築制限が行われ、土地利用がコントロールされます。
原則として、用途地域が設定されるのはこの都市計画区域内です。
街の秩序を保つためのシステムといった感じ。市町村や都道府県など、行政区画を超えて指定することができるのが特徴都市計画区域の種類
都市計画区域は、大きく3つに分かれます。
● 市街化区域
- 「すぐに市街地として整備していく地域」
- 住宅や商業施設、工場などを計画的に建てていく
- 用途地域、建ぺい率、容積率などの細かいルールが設定される
- 土地取引や開発行為には許可が必要になるケースが多い
いわば「これから街を作っていくエリア」のこと!
● 市街化調整区域
- 「市街化を抑制する地域」
- 原則として建物を建てることはできない
- 例外的に農家の住宅や公益施設などが認められる場合がある
- 大規模な宅地開発や商業施設建設は基本的に不可
「基本は建てさせないエリア」と覚えるとわかりやすい!
● 非線引き区域
- 市街化区域・市街化調整区域に線引きされていない地域
- 人口規模が小さい市町村などで設定される
- 市街化の方向性が明確でないため、個別に開発許可が必要になることが多い
- 用途地域が設定される場合もあるが、市街化区域ほど厳しくない
→ 「自由っぽいけど、実は制限もあるエリア」とイメージしよう!
都市計画区域外とは?
都市計画区域に指定されていないエリアも存在します。
- 山間部や離島、農村部など、人があまり住んでいない地域に多い
- 都市計画法による規制は基本的にかからない
- ただし、農地法、森林法、景観法など、他の法律による規制を受ける場合がある
都市計画区域外だからといって、完全に自由に開発できるわけではないことに注意が必要です。
勉強するときのコツ・イメージ

用途地域などの理解を深めるためにも、まずは都市計画区域の分類をイメージで押さえるのがおすすめです。
- 市街化区域=家やビルが建つ場所
- 市街化調整区域=原則建てられない場所(開発ストップ)
- 非線引き区域=田舎っぽいけど一応制限がある場所
- 都市計画区域外=基本自由だけど他法令注意
地図を思い浮かべながら「このあたりはどの区域だろう?」と想像するだけでも、知識の定着度が変わります!
用途地域と一緒に勉強すると効率的かもまとめ
都市計画区域は、街を守り、育てていくための出発点です。
この区域があるからこそ、住宅地や商業地、工業地といったエリアが計画的に整備され、快適な都市生活が実現します。
用途地域や建築規制を学ぶうえでも、まずは都市計画区域の考え方をしっかり押さえておきましょう。
そして、机の上だけでなく、実際に街を歩いて「ここは市街化区域かな?」「この田舎道は非線引きかな?」と考えてみると、さらに理解が深まります!
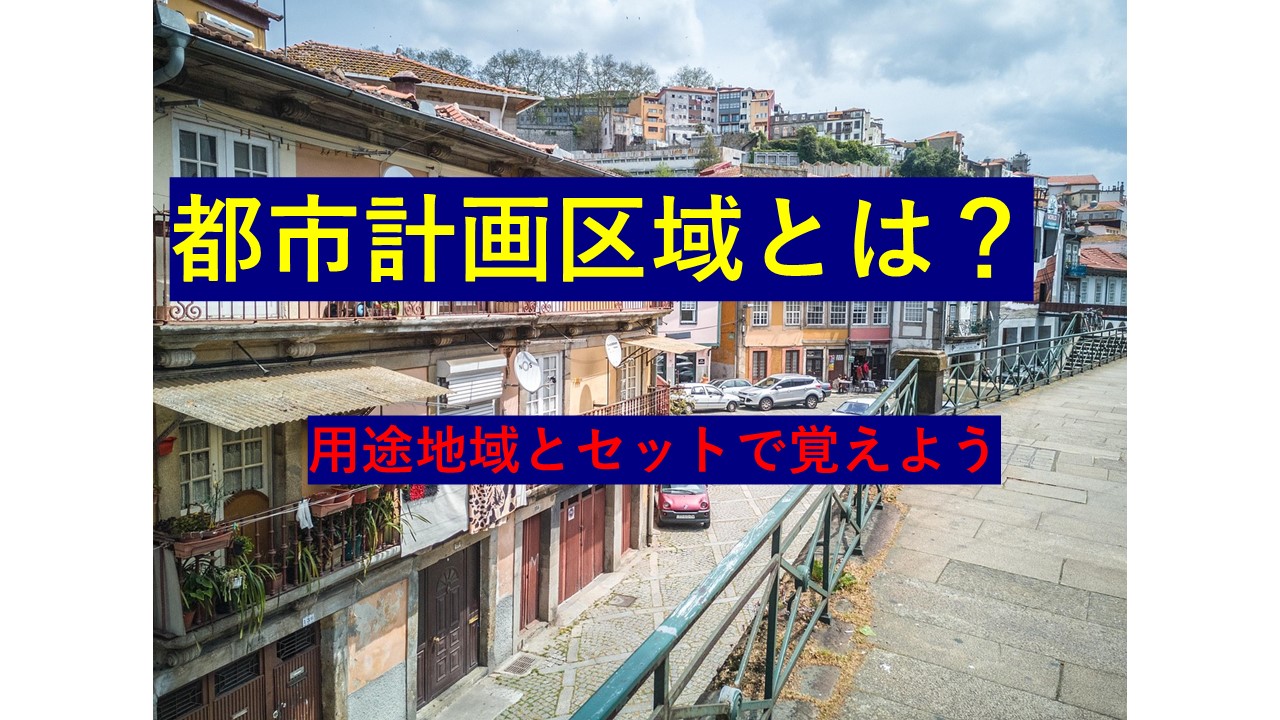

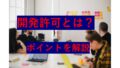
コメント