不動産・法律系の資格にはさまざまなものがありますが、「宅建」と「行政書士」「マンション管理士」「社会保険労務士(社労士)」の違いがわからず、どれを取るべきか迷う人は多いのではないでしょうか。
✅この記事では、それぞれの資格の難易度・試験内容・活かせる仕事・年収感などを比較しながら、どんな人にどの資格が向いているのかをわかりやすく解説します。
1. 各資格の基本比較
| 項目 | 宅建士 | 行政書士 | マン管士 | 社労士 |
|---|---|---|---|---|
| 受験資格 | なし | なし | なし | なし(実務 or 学歴要件あり) |
| 合格率 | 約15〜17% | 約10〜15% | 約8〜10% | 約6〜7% |
| 勉強時間目安 | 300〜400時間 | 600〜800時間 | 500〜700時間 | 700〜1000時間 |
| 試験時期 | 10月 | 11月 | 11月 | 8月 |
| 主な活用先 | 不動産会社、営業 | 法律事務所、行政手続き代行 | 管理会社、コンサル | 社労士事務所、企業の労務部門 |
| 独立可能性 | △ | ○ | △ | ◎ |
2. 宅建と他資格の違いと相性
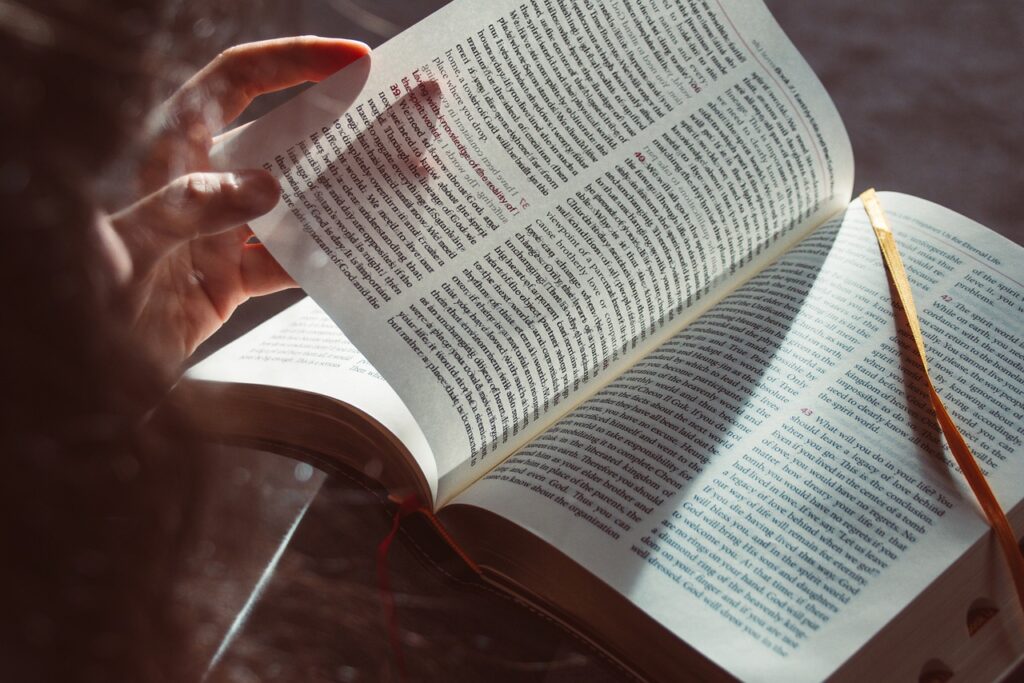
続いて、宅建とほかの資格との相性を見ていきます。
宅建 × 行政書士
- 両方とも法律知識が土台にあるので相性良し
- 宅建が不動産実務寄り、行政書士は法務・手続き寄り
- 宅建→行政書士の順で取る人が多い(法令の基礎が活かせる)
行政書士は独立実現性と試験難易度のバランスがちょうどよいので独立を考えている人にはお勧め。
宅建 × マン管士
- 範囲が一部重なる(法令上の制限・区分所有法など)
- 宅建合格者はマン管士の受験資格が不要に
- ダブルライセンスで管理会社への就職・転職が有利になるケースも
宅建 × 社労士
- 分野は違うが「会社の労務」と「不動産」は実務上つながることも
- 社労士の方が難易度はかなり高め(受験要件あり)
- 宅建合格後に「もっと国家資格を取りたい」と思う人が挑戦することも
3. どれを選ぶべき?タイプ別おすすめ

「まずは就職・転職で使いたい」
→ 宅建一択。業界ニーズが高く、受験資格なし、学習時間も比較的短い。
「法律知識を武器に独立も視野に入れたい」
→ 行政書士 or 社労士。ただし時間と根気が必要。宅建でまず基礎固めを。
「不動産業界で専門性を深めたい」
→ 宅建 → マンション管理士の順。管理会社・賃貸経営との親和性が高い。
4. 私の体験:宅建を先に取ってよかった理由
私はまず宅建からスタートしました。
理由は、「不動産の世界に関心があったこと」「勉強範囲が明確で独学でも手が届きそうだったこと」の2つです。
実際に宅建に合格したことで、法律系の勉強に対するハードルが一気に下がり、「もっと上の資格にも挑戦してみたい」と思うようになりました。宅建は、まさに“登竜門”という言葉がぴったりの資格です。
私が宅建の資格を取得しようとした最初のきっかけは、こちらの記事からどうぞ
まとめ:宅建を軸に、自分に合った資格を選ぼう
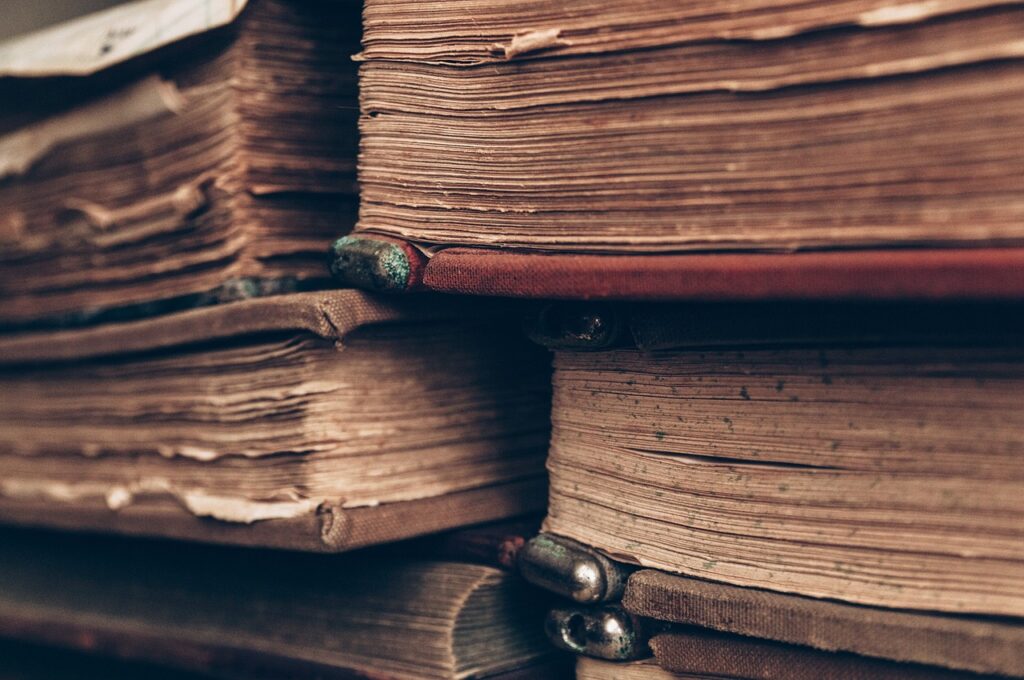
不動産・法律系の資格は、それぞれに特徴があります。
自分がどんなキャリアを描きたいかによって、選ぶべき資格は変わってきます。
とはいえ、「まずは宅建から始めてみる」というルートは非常におすすめです。
宅建を通して学ぶ基礎知識や勉強習慣は、今後の資格取得やキャリア設計にも必ず役立ちます。
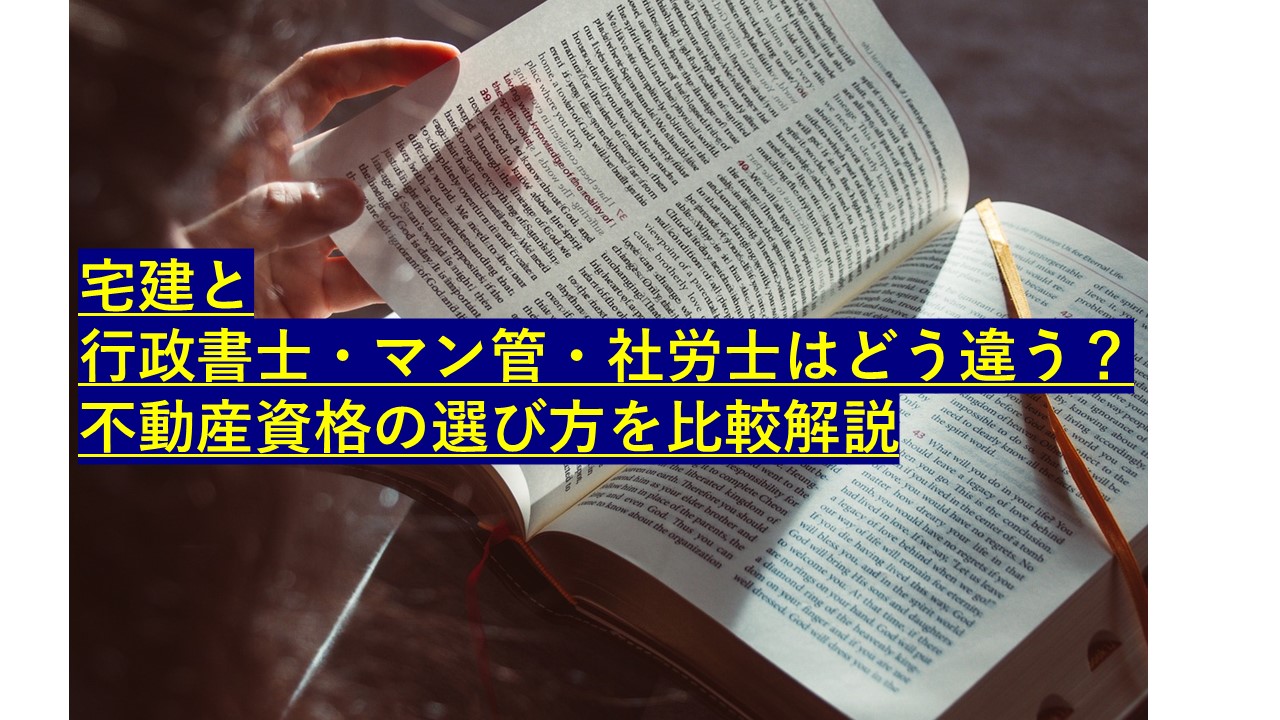



コメント