2025年の不動産鑑定士・短答式試験を受けられた皆さん、本当にお疲れさまでした。
不動産鑑定士は数ある国家資格の中でも難易度が高く、1年〜2年以上の勉強期間を必要とする資格です。
その第一関門ともいえる短答式試験が終わった今、少し気持ちが落ち着いている方も多いのではないでしょうか。

私は今年、短答式試験を受けていません。
ですが、来年に向けて日々着実に準備を進めています。
✅この記事では、「今年の試験をあえてスキップした」私が、来年合格を見据えて行っている5つの取り組みを紹介します。
これから受験を考えている方、または今回の結果に納得できなかった方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。
※本記事はアフリエイト広告を掲載しています。
1. 宅建で学んだ基礎を、鑑定士の土台として活かしている

私は大学2年生のときに宅建士試験を受け、合格しました。
宅建では不動産取引の基本的な法律(民法・宅建業法・借地借家法など)を一通り学ぶため、不動産鑑定士試験でもその知識は少なからず役立ちます。
たとえば、「不動産に関する権利関係」や「取引事例比較法」などの論点は、宅建の理解があるとある程度スムーズに入ってきます。
先に宅建を受けたことで、鑑定士のテキストが「初見じゃない」と感じられる部分が多く、精神的ハードルもかなり下がりました。
ただ、行政法規に関しては、都市計画法、建築基準法など宅建でも取り扱った法律が出てくるので最初は安心だと思っていましたが、難易度の違いに驚きましたね。
宅建士と不動産鑑定士の違いについては、こちらの記事をどうぞ
2. 鑑定評価基準の音読を習慣化している
不動産鑑定士の必須科目「鑑定理論」では、鑑定評価基準の丸暗記が求められると言われています。
私は今、鑑定評価基準の音読を毎朝のルーティンに組み込んでいます。
最初は意味が分からなくても構いません。
繰り返し声に出すことで、「見たことある」「聞いたことある」状態を作っておくことが目的です。
一文一文にリズムをつけたり、録音して聴き返したりすることで、定着率もアップします。
この積み重ねが、来年の本番で大きなアドバンテージになると信じています。
音読の重要性はこちらで解説しています↓
3. Notionで「復習スケジュール」と「過去問記録表」を作っている
私はNotionというノートツールで、勉強の記録とスケジュール管理をしています。
たとえば、
- 過去問を1問ごとに正誤・復習予定日を記録する「復習表」
- 行政法規や鑑定理論のインプットに使う「音読チェックリスト」
- 試験までの長期スケジュール(現実ライン・理想ラインを分けて可視化
などを作って運用しています。
計画を立てたはずなのに忘れてしまったり、復習のタイミングを逃してしまったりすることを防げるので、個人的にはかなりおすすめです。

計画を立てて終わってしまうのが一番もったいないですからね
4. 短答式の試験問題を確認し、傾向を分析している

試験を受けなかったとはいえ、過去問や今年の問題には必ず目を通しています。
最近はX(旧Twitter)や資格スクールのブログなどでも「今年の問題の難易度」や「出題傾向」に関する情報がリアルタイムで出てくるので、それらを参考に「来年に向けて対策すべきポイント」をリスト化しています。
このように、実際に試験を受けていなくても、「試験分析」はできるんだと感じました。
5. 「受けない年にしてよかった」と思えた理由を言語化している
私は今年、大学の授業やバイトなどとの兼ね合いもあり、あえて受験を見送りました。
結果的にこの判断は正解だったと思っています。
なぜなら、今は焦らずに「勉強スタイルを確立すること」に集中できているからです。
もし無理に今年受けていたら、インプットだけで終わってしまい、手応えのないまま試験を終えてモチベーションが下がっていたかもしれません。
今年はあえて受けないことで、長期的に勝ちにいく準備ができていると実感しています。
試験を受けない年でも、やるべきことはたくさんある
不動産鑑定士は短期決戦ではなく、長期戦です。
だからこそ、「受験しない年」は決してムダではなく、むしろ「合格までの大事な一歩」として活かせるタイミングだと思っています。
私自身もまだまだこれからですが、この記事が、来年以降の合格を目指す誰かの参考になれば嬉しいです。
私が不動産鑑定士を目指す理由はこちらからどうぞ
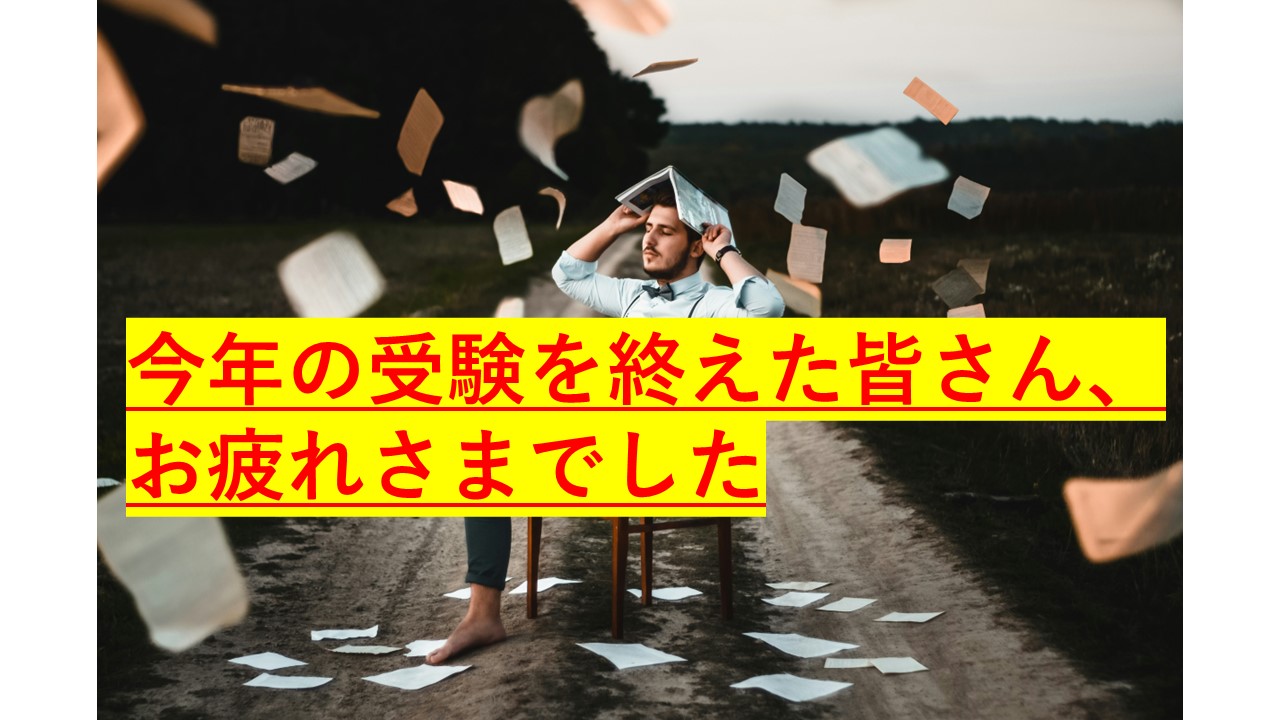
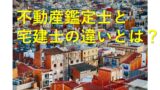
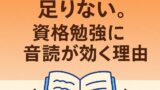



コメント