宅建試験の勉強で「一問一答」を使っている方は多いと思います。
ただ、何となく解いて終わりにしていませんか?
私は、一問一答を「記録学習ツール」として活用することで、短期間で得点力を底上げすることができました。
特に活躍したのが宅建士合格のトリセツシリーズの一問一答です。
✅今回は、私が実践していた「正答率の記録法」と、トリセツ一問一答の使い倒し方を、具体的に紹介します。
※本記事はアフィリエイト広告を掲載しています(アマゾンを含む)。
なぜ一問一答に「記録」が必要なのか?
一問一答はアウトプットに最適な教材ですが、解くだけでは知識は定着しません。
大切なのは、「できたかどうか」「なぜ間違えたか」を把握し、それを復習につなげることです。
記録を残すことで、次のようなメリットがあります。
・自分の苦手分野が明確になる
・復習の優先順位がつけやすくなる
・勉強の積み重ねを可視化できる
・「わかったつもり」を防止できる
宅建試験は「覚えていれば解ける」問題が大半です。
つまり、どこで覚えきれていないかを可視化することが、合格への近道なのです。
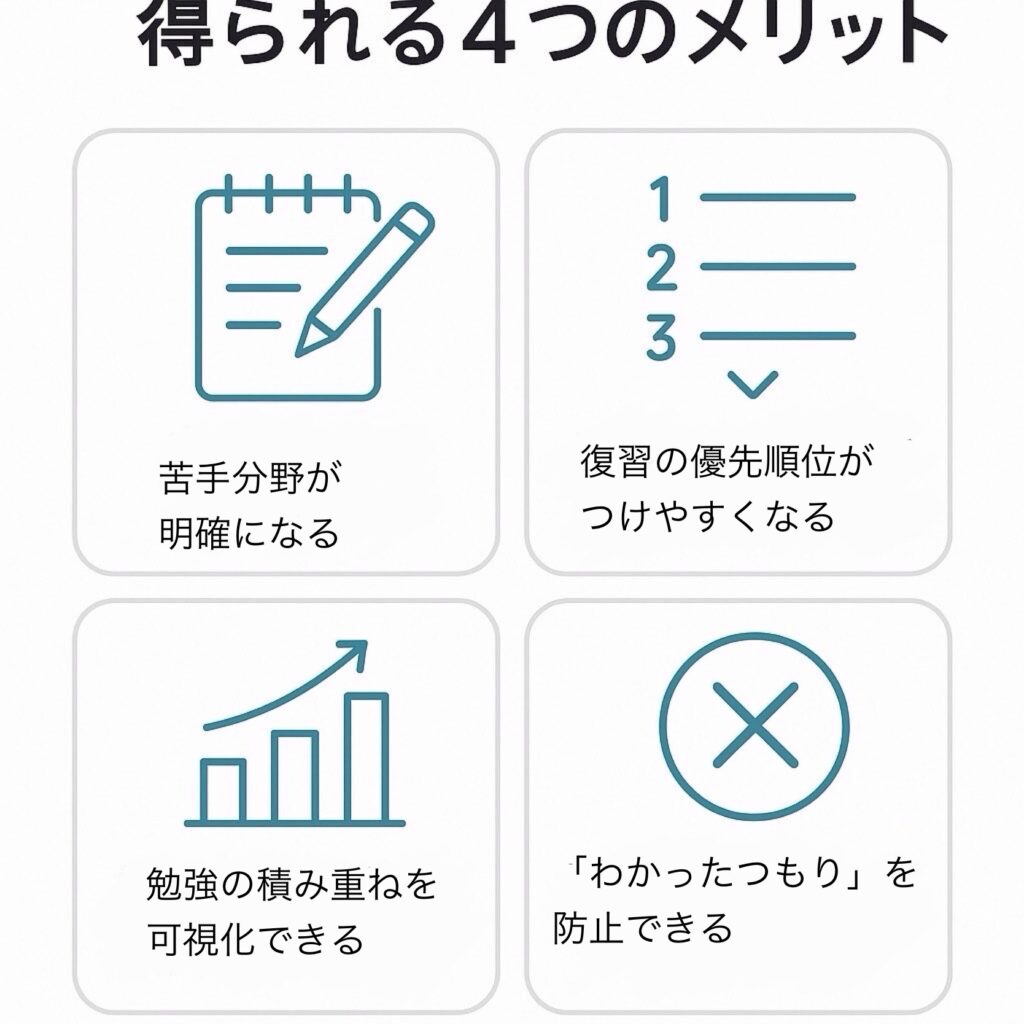
私のやり方:トリセツ巻頭の「目次」を正答率チェック表にする
トリセツの一問一答には、巻頭に分野ごとの「目次ページ」があります。
私はそこを、正答率の記録表として活用していました。
具体的な使い方
- 各章(例:都市計画法、重要事項説明、所得税など)の横に、「1回目:72%」「2回目:89%」のように正答率を記入
- 回を重ねるごとに、改善しているかどうかを比較
- 正答率が70%未満の分野にはマーカーを引く(復習対象)
- 全体を見渡して、苦手が集中しているテーマを優先的にやり直す
この方法はとにかく一目で弱点がわかるのがポイントです。
「まだ民法が曖昧だな」「業法はもういける」などが、感覚ではなく数字で把握できるようになります。
本文では〇×△チェック+メモ

各問題については、以下のような感じでチェックをつけていました。
- 〇:自信を持って正解できた
- △:迷ったけど正解(あいまいなので再チェック)
- ×:間違えた問題(解説をしっかり確認)
さらに、間違えた問題には短くメモもつけておきます。
例:
- 「語尾の違いに注意」
- 「◯年以内→◯ヶ月以内、ケアレスミス」
- 「例外ルールを見落とし」
これを繰り返すことで、同じミスを防ぎやすくなり、復習効率がどんどん上がっていきます。
使っていたのは『宅建士 合格のトリセツ 一問一答』
私が実際に使っていた教材がこちらです。
おすすめポイント
- 過去問をベースにしているので、試験に出るツボがわかりやすい
- 解説が簡潔で、必要な知識に絞って覚えられる
- コンパクトなサイズで、通学・通勤などのスキマ時間にぴったり
- 巻頭目次があることで、正答率の記録に使える唯一の一問一答集(これ地味に超便利です)
1冊でアウトプットから弱点管理まで完結できるのが、トリセツの大きな魅力でした。
スキマ時間にもぴったりの勉強法
この正答率記録法は、スキマ時間学習とも相性が抜群です。
- 通学中の電車内で10問解いて、正誤をチェック
- 帰宅後に正答率を目次に記録
- 寝る前に×問題だけ見直す
このサイクルを毎日回すことで、短時間でも効率的に力をつけることができます。
実際に感じた効果

このやり方を取り入れてから、以下の変化を感じました。
- 復習の優先順位に迷わなくなった
- 苦手分野の正答率が上がり、全体の得点力が安定した
- 「あと何%で満点だ」という感覚が持てて、目標が具体化された
- 勉強が“作業”ではなく“戦略”になった
「やみくもに問題を解いていた頃」と比べると、同じ時間で得られる成果が全然違うと実感しています。
まとめ:目次を活用して、宅建を攻略しよう
宅建試験の勉強で大切なのは、自分の弱点に気づき、対策を取ることです。
そのために一問一答を使うなら、ぜひ「記録」と「分析」をセットで取り入れてみてください。
トリセツは、巻頭目次を活用することで「自分専用の管理ツール」に進化します。
あなたも今日から、トリセツ一問一答で「見える化学習」を始めてみませんか?
おまけ:余談ですが基本テキストは合格へのトリセツ基本テキストを使用していました。
こちらの記事でも紹介しています。テキストの特徴を、独学で勉強する人向けに解説しているので、チェックしてみてください。
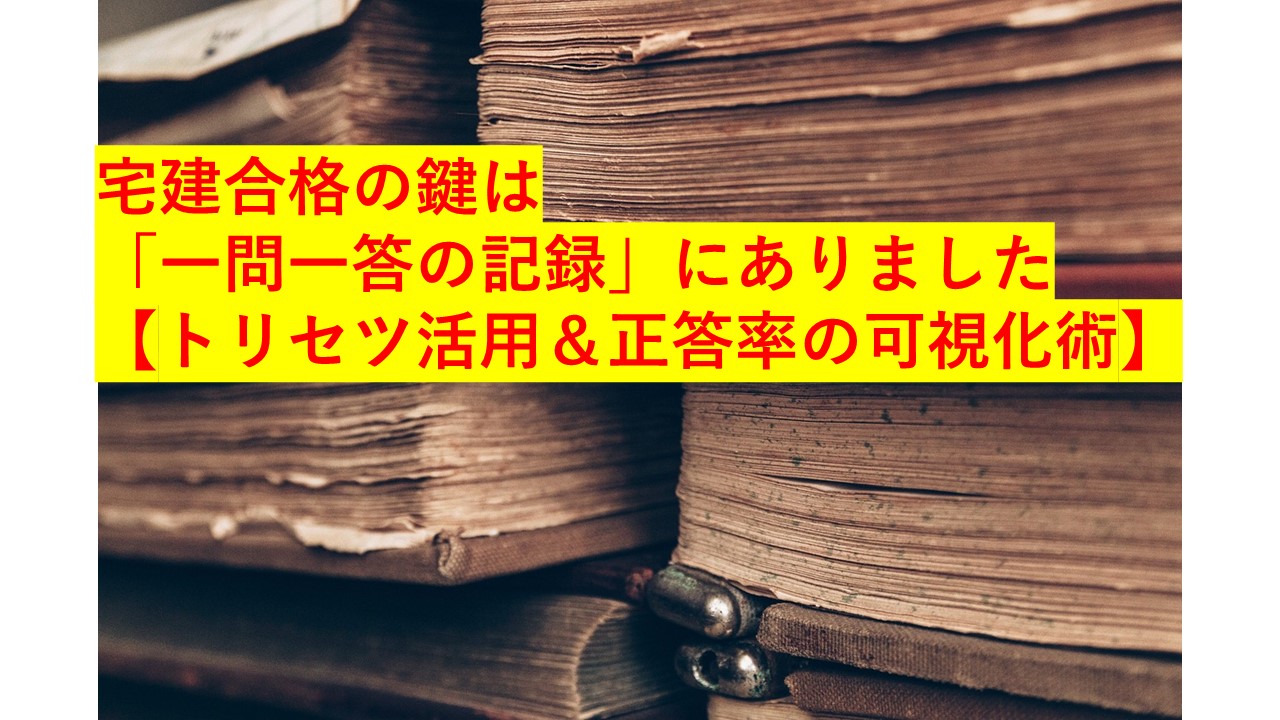



コメント