宅建の独学を始めたばかりのころ、私はまずテキストを開いてこう思いました。
「……情報多すぎて、全部覚えられる気がしない」
でも、ちゃんと“使い方”を工夫すれば、テキストはただの紙の束じゃなくて、「合格を引き寄せる武器」になります。
✅この記事では、私が実際にテキストをどう使い込んだかを紹介していきます!
※本記事は、アフィリエイト広告(アマゾンを含む)を掲載しています。
私が宅建合格まで使い倒したのは『合格のトリセツ』
フルカラーで薄め、見た目もやさしそう。
最初は「とっつきやすそうだから」という理由で選びました。
でも、読み進めると、要点がギュッとまとまっていて、初学者の私にはぴったりでした。
そして何より、書き込み欄やなど、「育てるテキスト」としての使いやすさが神でした。
私が使用したテキストはこちら↓
読むだけじゃ足りない。こうやって使い込んだ!

テキストは“見る”だけだと頭に入ってこない。
だから私は、以下のようにして使い込みました。
● 1周目:軽く通読+重要語句をマーキング
まずはサクッと読みながら、気になった用語や見出しをマーカーでチェック。
図解や色分けされたポイントは、眺めるように何度も確認。
あまり気負わず、1〜2週間で1周する感じで進めました。
ここの段階では、全体像の理解が大事。細かい理解は不要なので、サクサク進めましょう。
● 2周目:音読+要点まとめ
朝の時間に20分ずつ、音読しながら要点を再確認。
付箋を使いながら、視覚+音で覚えるよう意識。
ページの余白には、自分の言葉でまとめや補足を書き込んでいきました。
● 3周目以降:問題集と連携
一問一答や過去問を解いたあと、「ここどこだっけ?」ってなったらテキストに戻る。
これ以降は一問一答をメインの教材として、わからないところやあいまいな問題に出会ったときにテキストに戻るような感じで取り組んでいましたね。
テキストに“自分の言葉”で書くのが最強だった

私はけっこうマーカーを使う派だったけど、それ以上に効果があったのは「自分の言葉で書く」ことでした。
とくに民法は、ただ読むだけだと難しい。
でも、「これは○○の話ってことだよね」みたいに、自分なりに書き込むと、後から読み返したときの理解度が全然違いました。
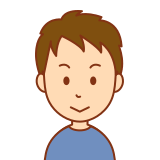
「やってる感」が自信につながったと思います。
「トリセツ」を使うときにちょっと注意したいこと
情報がコンパクトにまとまっている分、少しだけ注意点もあります。
- 細かい知識や例外はあまり載っていないことがある
- 簡潔だからこそ、補足は自分で調べたり、書き込んだりするのが前提
「このページ、内容薄いな」と思ったところは、付箋やノートで補完してました。
でも、逆にそれが“使い倒す”という感覚にもつながって、結果的には良かったと思ってます。
『トリセツ』については、こちらの記事でも紹介しています!
読むだけのテキストから、合格を引き寄せる“武器”に

テキストを眺めているだけだと、なんとなく勉強した気になって終わっちゃいます。
でも、書いて、声に出して、問題にリンクさせて、テキストを「自分だけの参考書」にする。
これが、私の宅建合格の一番の近道だったと思います。
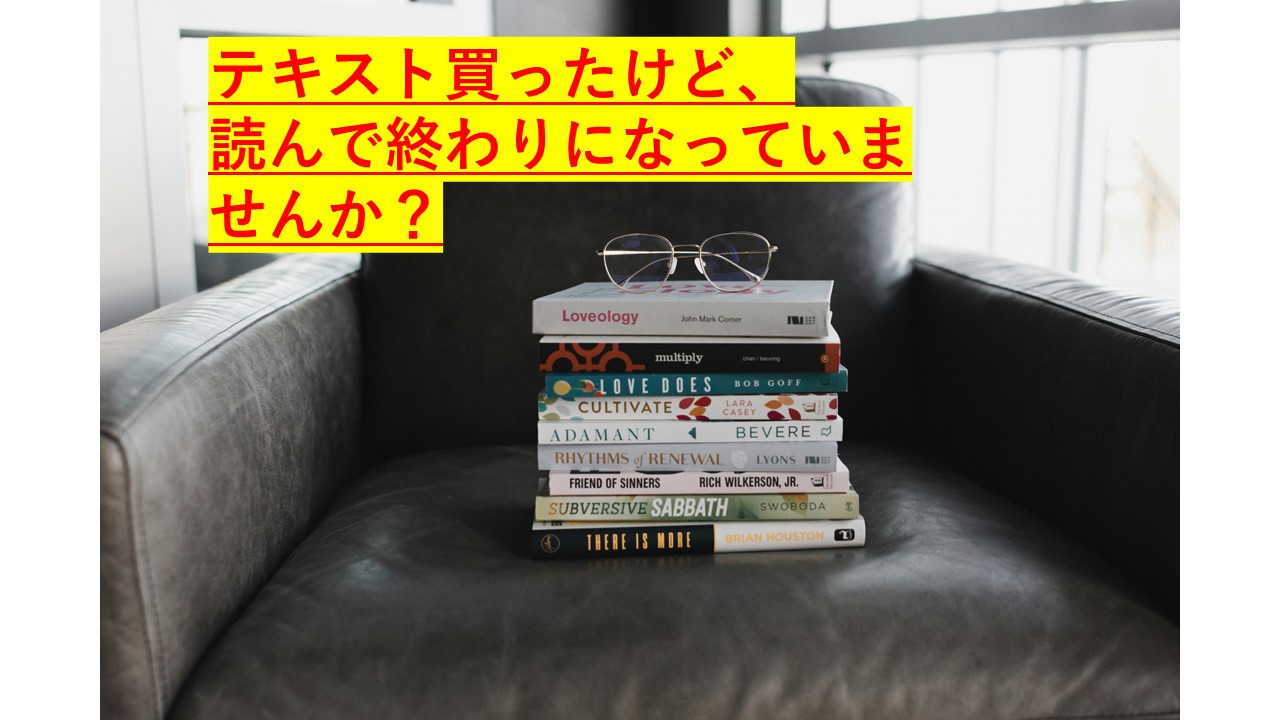



コメント