こんにちは、ハルです。
勉強は、結局「続けられるかどうか」がすべてだと思います。
私自身、最初は習慣化なんてまったくできませんでした。 勉強したい気持ちはあるのに続かない。罪悪感だけが積み重なる。 そんな日々が続いていました。
しかし、宅建の受験をきっかけに「やるしかない状況」に身を置いたことで、 少しずつ習慣が“行動”になり、“当たり前”になってきました。
この記事では、私が勉強を習慣にするまでにやってきたこと、 そして続けるための工夫を、具体的に紹介してみようと思います。
最初は全然続きませんでした
- 机に向かっても集中できない
- 「今日はいいか」と思ったら1週間サボる
- やらない自分に落ち込む
そんな状態でした。
ですが、宅建の試験が近づくにつれて、「やるしかない」という状況ができました。 夏休みの時間をすべて勉強に充てて、とにかく机に向かいました。
最初は、「1日〇時間やらなきゃ」と気負いすぎて、逆に続かなくなることも多かったです。 でも、毎日完璧にやろうとしないこと、自分に合った“型”を作ることが、 習慣の第一歩になるのだと、だんだんと実感するようになりましたね。
習慣化に役立った5つの工夫
① 3段階のタスク管理
毎日の勉強を、
- 最低ライン(絶対にやる)
- 現実ライン(できそうな量)
- 理想ライン(できたら嬉しい) に分けて考えるようにしました。
「全部やる」ではなく、「最低だけは必ずやる」と決めておくことで、 気持ちが楽になり、継続へのハードルが下がります。「最低ラインだけの日」が続いても、それは“ゼロじゃない”という事実になります。 この感覚は、私にとってとても大きかったです。
② 朝のルーティンを固定する
朝起きたら、
- 昨日の復習(20分)
- コーヒーを淹れる
- 家事や軽い読書
- 机に向かって1時間
という流れにしています。
この「流れを決めておく」ことが、習慣の土台になりました。 人は、始めるまでが一番面倒です。だからこそ、「迷わず動ける」導線をつくることが重要です。
朝に勉強をすることで、1日が少しだけ整う感覚もあります。③ スキマ時間の“定位置”をつくる
・バイト前の15分は行政法規の音読 ・通学中は基準のチェックリストを確認
スキマ時間は、何もしないと本当にすぐに過ぎてしまいます。 でも、あらかじめ「この時間はこれをやる」と決めておけば、 その時間が“目的のある時間”に変わります。
「まとまった時間が取れない日でも、何かはできた」 という安心感が生まれ、自己肯定感にもつながりました。
④ 記録を残す
- Notionで過去問の正誤を記録
- X(旧Twitter)で積み上げを発信
勉強の記録は、ただのメモではなく「自分との対話」でもあると感じています。
何をやったのか、何ができなかったのか。 自分の進み方を可視化することで、「今、どこにいるか」がわかるようになります。
また、発信することによって、自分の言葉で勉強を整理できるのも大きなメリットです。
⑤ 0か100じゃなく、1でもOK
「今日はこれだけしかできなかった…」ではなく、 「今日はこれだけできた」と考えるようにしています。
この考え方を持つようになってから、 「今日は無理せず最低ラインだけやって寝よう」と思えるようになりました。それでも、「継続できた」という実感は失われません。
勉強が続かない最大の原因は、「できなかった日=ダメな日」として切り捨ててしまうことだと思います。
そうではなく、たとえ1問でも、1ページでも、少しでもやれたなら、それで十分。 この感覚を持てるかどうかが、習慣化のカギだと感じています。
習慣化して変わったこと
- 勉強を「やるかやらないか」で迷わなくなった
- 忙しい日でも「最低限」は守れるようになった
- やったことを記録すると、自分に自信がついた
- 習慣は、行動よりも“考え方”から作られる
以前は「時間がある日しか勉強できない」と思い込んでいましたが、 今は「どんな日でも最低限はやれる」ようになりました。
それによって、自分に対しての信頼感が育ってきた気がします。
「私は続けられる人間だ」と、自分自身に言えるようになったことが、 一番の成果かもしれません。まとめ:習慣は“努力”ではなく“仕組み”
勉強を習慣にするには、強い意志や完璧な計画は必要ありません。 自分が「できる形」にすることが、いちばん大切だと思います。
習慣とは、努力の継続ではなく、選択の積み重ねです。もし今、「続かない」と悩んでいる方がいたら、 完璧を目指すのではなく、“戻ってこられる習慣”をつくってほしいです。
そして、今日の1ページが、未来の自分にとっての“当たり前”になりますように。
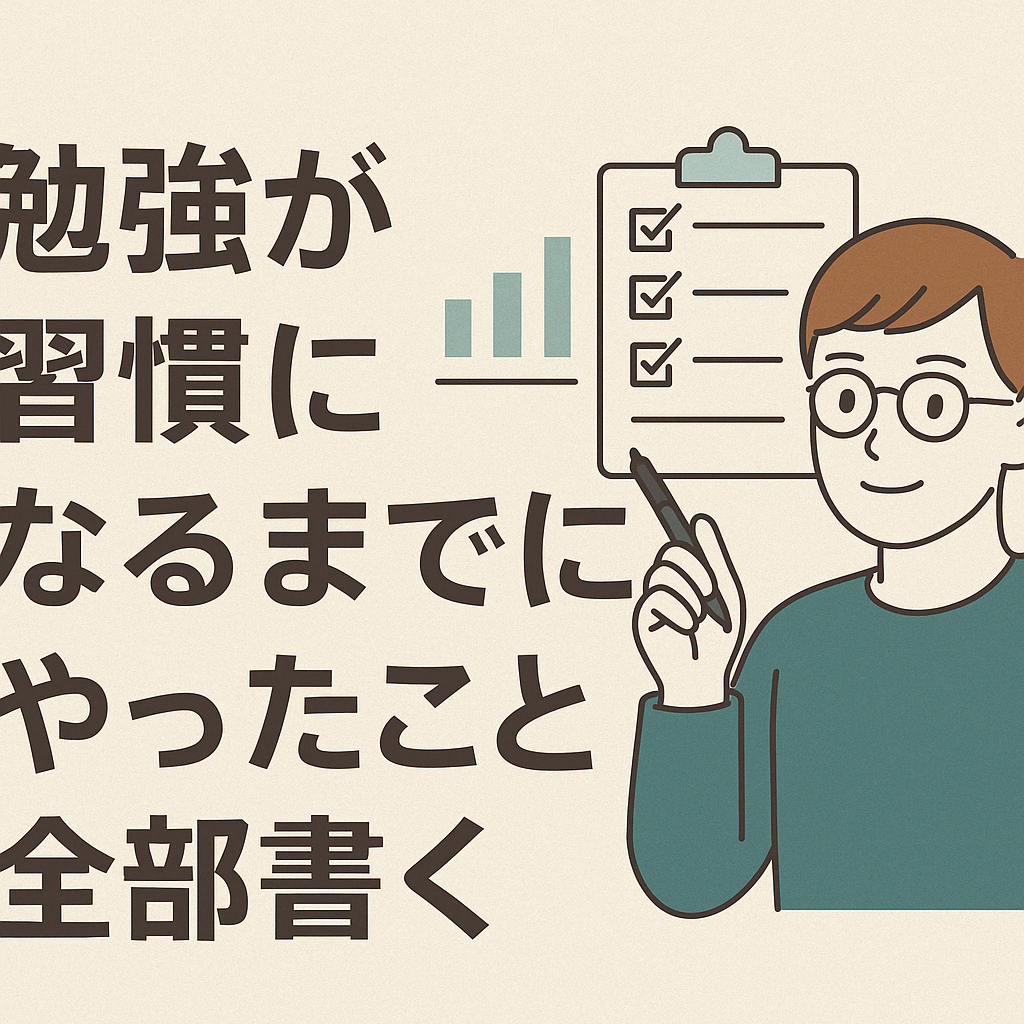

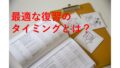
コメント